ゴリラたちの一年
上記のジョンさんの手紙にもありましたが、この1年はゴリラたちにとって過酷な試練の時期でした。1996年10月に勃発した内戦は12月には鎮静化したものの、多くの難民がカフジ・ビエガ国立公園へ逃げ込み、野生動物と人間との戦いはむしろ激化しました。公園の職員が武器をもてなくなったおかげで密猟が横行し、半年もの間公園内ではゾウ撃ちの銃声が絶えず鳴り響き、ワナが至るところに仕掛けられる事態となりました。
内戦で多くの畑が踏みしだかれ、大量の家畜が殺されたり略奪されて失われました。日々の食料を得るために人々は先を争って公園へ侵入し、野生動物を狩り立てたのです。最も大きな痛手を被ったのはゾウで、山地林にすむゾウたちの半分以上が犠牲になったと思われます。ゴリラは比較的被害が軽かった方ですが、それでもいくつかの地域でゴリラの死体が発見されており、最もよく保護されているはずの公園入り口近くでもゴリラが殺されています。
最初の悲劇は1997年の4月にムシャムカ集団で起こりました。この集団は1971年以来その動向が調べられていて、シルバーバックのムシャムカは当時すでに十分に成熟していましたから、事件が起きた時もう優に40才を超えていたと思われます。ゴリラの40才は人間の60才にあたり、ムシャムカは相当な老齢と推測されました。たしかに胸の筋肉が落ち、首のあたりに多くのしわが寄って、全身がかなり骨ばって見えていました。そんなわけで、ムシャムカの死亡が伝えられた時、私たちは誰もが老衰で死んだものと考えたのです。
ところが、その後の調査でどうやらムシャムカは密猟者に殺されたようだということがわかりました。当時はまだ新政府が樹立される前の戒厳令下で、ガイドたちもゴリラに会いにいくことができませんでした。そのため、聞き込みによって事情が明らかになってくるまで、現場の様子すら調べることができなかったのです。今になっても、ムシャムカの死体は見つかっていません。
ムシャムカが死んだ時、集団にはまだ背中が白くなっていない2頭の若いオスと、3頭のメス、それに3
頭の子供たちがいました。こんな若いオスたちではとても集団をまとめていけないだろうと思われましたが、意外なことにメスたちがよくまとまって暮らしはじめ、1年たった今でも集団は崩壊していません。そして驚いたことに、その後3頭のメスがそろって赤ん坊を出産したのです。おそらく3
頭ともムシャムカの子供と思われます。何とか無事に育ってほしいものです。
マエシェ集団は現在2代目のマエシェによって率いられています。このシルバーバックは以前はラムチョップと呼ばれていたムシャムカの息子です。初代のマエシェが数年前に死んだ後、何度もこの集団を訪問してはメスたちのご機嫌をうかがい、やっとリーダーとして認められることになったのです。しかし、2代目マエシェはまだ若く、メスたちは全幅の信頼を置いているわけではないようです。それを証拠に、マエシェとメスの交尾はほとんど観察されていないし、メスもまだ出産してはいないのです。採食中マエシェはメスたちに置いてきぼりをくうことが多く、よくひとりぼっちで食べている姿が見受けられました。でも、最近入ったニュースによると、マエシェが立て続けに複数のメスと交尾をしているようなので、やっとメスたちもマエシェを信頼すべきパートナーとして認めはじめたと言っていいでしょう。この分なら、近いうちにベビー・ブームになるかもしれません。
2番目の悲劇は1997年の10月に起こりました。ジョンさんの手紙にあるように、人に最もよく馴れていたニンジャが兵隊に撃たれてしまったのです。ニンジャはまだ24才で働き盛りでした。これから数々のドラマをつくっていくと期待されていたのに、本当に残念です。ニンジャが健在だった頃13頭いたメスも11頭に減りましたが、まだメスと子供あわせて21頭が一緒に暮らしています。若いオスが1頭もいないのが気掛かりです、強くてやさしいシルバーバックが早くこの集団に加わってほしいものです。 |
ムバララ集団は、人馴れした集団のなかで唯一オスを密猟者に殺されなかった集団です。ムバララもそろそろ老齢に達しようとしていますがまだまだ元気で、子供たちの信頼を一身に集めています。最近マエシェ集団からメスが移ってきていますから、メスにもなかなか人気があると考えていいでしょう。ただ、ジョンさんの報告ではムコノという子供が両手をワナで絞められ、失ってしまうのではないかと心配です。この集団も密猟者の脅威から免れることはできなかったのです。
これらの集団の最近の様子は今年4月にTBS の「神々の詩」で放映されました。再放送されるかもしれませんので、まだ見ていない方はぜひごらんください。1996
年の6月にコンゴ、アメリカ、日本の合同チームが行った調査では、山地林約600平方キロメートルにゴリラは約240頭生息していました。この数は1990年に行われた調査(約260頭)に比べて少し減っていました。今はいったい何頭が生き残っているのか、全く見当がつきません。ひょっとしたら悲惨な数字になるのかもしれませんが、とにかく早急に生息状況を調べて現状を把握し、保護の対策を講じなければなりません。そのために、まず政治状況が好転し、早く私たちが協力して調査ができる日がくることを願っています。
(1998年5月 山極寿一)
| |
年
|
シルバー
バック
|
ブラック
バック
|
オトナ
メス
|
コドモ
|
乳児
|
計
|
ムシャムカ集団
の
構 成
|
1996
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
9
|
|
1997
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
8
|
|
1998
|
0
|
1
|
4
|
1
|
3
|
9
|
マエシェ集団
の
構 成
|
1996
|
1
|
0
|
4
|
2
|
3
|
10
|
|
1997
|
1
|
0
|
9
|
2
|
3
|
10
|
|
1998
|
1
|
0
|
10
|
6
|
0
|
17
|
ニンジャ集団
の
構 成
|
1996
|
1
|
0
|
13
|
6
|
6
|
26
|
|
1997
|
1
|
0
|
13
|
7
|
6
|
27
|
|
1998
|
0
|
0
|
11
|
5
|
5
|
21
|
ムバララ集団
の
構 成
|
1996
|
1
|
0
|
10
|
3
|
3
|
17
|
|
1997
|
1
|
0
|
13
|
3
|
4
|
21
|
|
1998
|
1
|
0
|
13
|
3
|
4
|
21
|
ポポフ展と講演会のお知らせ
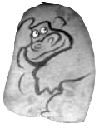 1998年 1998年
6月9日(火)〜14日(日)
「ゴリラ・ゴリラ・ゴリラ」
早川篤の石のゴリラ作品展
■堺町画廊(京都)
6月16日(火)〜21日(日)
「コンゴ・コンゴ・コンゴ」
コンゴのアートとポポフ展
■堺町画廊(京都)
6月20日(土)14:00 より 参加費1,000 円
シンポジウム「コンゴの森と音楽」
■堺町画廊(京都)
バサボセ・カニュニ
(コンゴ民主共和国中央科学研)
八木繁実(アフリカ音楽研究家)
大林 稔(龍谷大学)
沢田昌人(京都精華大学)
山極寿一(京都大学)
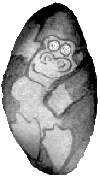 7月1日(水)〜12日(日) 7月1日(水)〜12日(日)
GAIAの会「ポレポレ基金」展
■ウイルあいち(名古屋)
7月5日(日)13:30 より
参加費2,000 円
講演:「ゴリラの森」
■ウイルあいち(名古屋)
バサボセ・カニュニ
(コンゴ民主共和国中央科学研)
7月7日(火)〜12日(日)
阿部知暁原画展
「ゴリラ雑学ノート」
■堺町画廊(京都) |


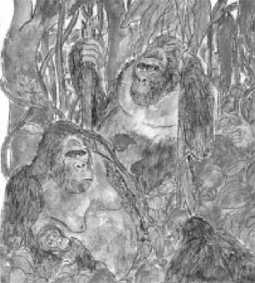
 日本に滞在している間、オギュさんは京都大学の研究者と共同で研究しているカフジ・ビエガ国立公園のゴリラとチンパンジーの生態についての資料を分析するかたわら、日本の人たちともいろいろ交流しました。滞在していた愛知県犬山市にある城東小学校でコンゴの子供たちや学校教育について話をしたり、民話を話して聞かせたり、愛知県内でおはなし会やおやこ劇場の活動をしている人々にコンゴの昔話について話をしました。コンゴには伝統的に昔話をする習慣があり、現在でも学校教育に使われたり、ラジオやテレビでもよく流されていて子供たちに圧倒的な人気があります。オギュさんもたくさんの昔話を知っていて、もうほとんど忘れたと言いながらもいくつかの興味深い話を披露してくれました。日本の昔話とも共通するところがあって面白いと言っていました。将来こういった昔話を通じて故郷を紹介し、日本とコンゴの子供たちが交流できればいいなあと思っています。 帰国した後、オギュさんは今まで通り中央科学研究所で哺乳類研究に従事していますが、まだ十分に治安が回復しておらず、あちこち自由に歩き回って調査ができない状況にあります。森の中にはゲリラが潜んでいると言われており、国立公園で調査をするには武装した兵士の護衛が必要です。自然保護を推進し、人と野生動物との共生をはかるためには、まず人と人とのトラブルを解決しなければなりません。
日本に滞在している間、オギュさんは京都大学の研究者と共同で研究しているカフジ・ビエガ国立公園のゴリラとチンパンジーの生態についての資料を分析するかたわら、日本の人たちともいろいろ交流しました。滞在していた愛知県犬山市にある城東小学校でコンゴの子供たちや学校教育について話をしたり、民話を話して聞かせたり、愛知県内でおはなし会やおやこ劇場の活動をしている人々にコンゴの昔話について話をしました。コンゴには伝統的に昔話をする習慣があり、現在でも学校教育に使われたり、ラジオやテレビでもよく流されていて子供たちに圧倒的な人気があります。オギュさんもたくさんの昔話を知っていて、もうほとんど忘れたと言いながらもいくつかの興味深い話を披露してくれました。日本の昔話とも共通するところがあって面白いと言っていました。将来こういった昔話を通じて故郷を紹介し、日本とコンゴの子供たちが交流できればいいなあと思っています。 帰国した後、オギュさんは今まで通り中央科学研究所で哺乳類研究に従事していますが、まだ十分に治安が回復しておらず、あちこち自由に歩き回って調査ができない状況にあります。森の中にはゲリラが潜んでいると言われており、国立公園で調査をするには武装した兵士の護衛が必要です。自然保護を推進し、人と野生動物との共生をはかるためには、まず人と人とのトラブルを解決しなければなりません。


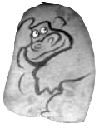 1998年
1998年
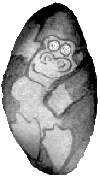 7月1日(水)〜12日(日)
7月1日(水)〜12日(日)